子供がサッカーを習い始めて、はじめて応援に行く場合、親としては本当にワクワクしますよね!
そしてワクワクと同時に何を持っていけば良いのか?どんな風に応援すれば良いのか?そもそもサッカーのルールもよくわからない…などなど、気になることはたくさんあると思います。
本記事では、サッカー観戦の際の服装や持っていくと便利な持ち物、サッカー観戦のコツなどをご紹介したいと思います。
サッカー観戦に適した服装

サッカー観戦を快適に過ごすためには、まずは服装を間違えないようにしましょう。
季節によらず気を付けるポイントと、夏と冬の服装をそれぞれご紹介していきます。
季節によらず気を付けるポイント
ここでは、季節によらず気を付けたほうが良いポイントをあげていきます。
衣服
サッカーは土のグラウンドで行うことが多いです。
公式戦の決勝戦などかなり勝ち上がらないと、プロのような芝のグラウンドで試合を行うことは出来ません。
土のグラウンドのため、どの季節でも砂埃がすごいです。。
ですので、ナイロン生地など砂埃を落としやすい衣服や洗濯のしやすい衣服をおすすめします。
靴
ヒールの高い靴はやめましょう。
芝を痛めるので、最悪の場合、グランドに入れず観戦出来ない場合もありますよ。
夏は風通しの良いサンダルを履きたくなりますが、スパイクを履いた子供に踏まれないように注意しましょう(笑)
また、直射日光を浴びて足もかなり日焼けするので気になる方は普通の靴を履いたほうが良いです。
夏ならば風通しの良いランニングシューズかグラウンドに出る場合はやはりトレシューが無難です。
冬は動かないので足元が本当に寒くなります。
アウトドアブランドの防寒靴を用意するとだいぶ楽になります。
量販店の安いプライベートブランドのものでも良いと思うのであると良いです。
末端冷え性の私は防寒靴+つま先が温まる靴用ホッカイロを愛用しています。
夏の服装
夏はとにかく暑いです。。
炎天下の中、直射日光に長時間さらされることも多いので、なるべく風通しがよく汗を吸収する服装が良いです。
帽子(サファリハット)
帽子はマストアイテムです。
ベースボールキャップも良いですが、出来ればより日差しを遮れるサファリハットと呼ばれている帽子がおすすめです。
サングラス
長時間強い日光を浴びると、眼球も日焼けしてしまい視力低下を招くと言われています。
写真撮影の場合などサングラスを外したい場合もあると思うので、サングラスストラップもあると便利です。
日傘
河川敷など日陰が一切ないグランドも多いため、日傘は絶対にあったほうが良いです。
日陰があるだけで暑さがだいぶ和らぎます。
出来れば、お父さんも使えるような男女兼用デザインの日傘だと使いやすいです。
クールネック
水に濡らすことで長時間にわたり首回りを冷やすことが出来ます。
首回りは血管が集中しているので、そこを冷やすことで冷やした血液を全身に行きわたらせることで熱中症予防になります。
レインコート
ゲリラ豪雨対策です。
普通のレインコートでも問題ありませんが、我が家では自転車用のレインコートをサッカー観戦にも使っています。
冬の服装
ここからは、冬の服装についてご紹介します。
子供たちは走り回るので冬でも割と問題ないですが、観戦する側は基本動かないので冬場は体がとても冷えてしまいます。
風邪をひかないようにくれぐれも服装には注意してください。
ベンチコート
最強の防寒アイテムです。
周りのコーチが冬になるとみんな着ているのも、その防寒性能の高さが理由なのです。
今年のモデルのベンチコートは高いですが、去年などの型落ちベンチコートであればお手頃価格なのでねらい目です。
手袋
子供と同じように手のひらに滑り止めが付いた手袋のほうが、荷物の搬送などを行いやすいので便利です。
また、スマホのタッチ画面対応の手袋もおすすめです。
サッカー観戦に必要な持ち物


ここからはサッカー観戦に必要な持ち物をご紹介していきます。
絶対に持っていくべき持ち物、あると便利な持ち物、この二つに分けてご説明します。
絶対に持っていくべき持ち物
大きいビニール袋
子供が脱いだ汗だくのユニフォームを入れるだけでなく、急な雨の時も荷物を入れられるので常に2,3枚用意しておくと便利です。
レジャーシート
荷物置きだけでなく、下の子供が寝てしまう場合などにも使えます。
水筒(夏であれば氷を忘れずに)
しっかり保冷出来て、少し大きめの水筒がおすすめです。
また、保温も可能な水筒であれば冬場は暖かい飲み物を用意することも出来ます。


熱中症予防グッズ
年々、サッカー観戦中に熱中症で倒れてしまう人が増えている気がします。
命に関わることなので、皆さん本当に気を付けてください。
しっかり塩分を補給できる飴やタブレット、首などを冷やすことが出来る急冷アイテムを準備しておいたほうが良いです。
手持ち扇風機
最近大流行の手持ち扇風機もあると助かります。
両手を開けられるように、ネックストラップが付いている手持ち扇風機が便利です。
虫よけスプレー
場所によっては、虫よけスプレーも必須ですね。
夏場は汗をかくので刺されやすいです。
トイレに流せるティッシュ
トイレがしっかり管理されていないグランドなども多いです。
トイレットペーパーが切れていたという悲劇を迎えないために、、トイレに流せるティッシュを持参しておくと色々助かります。
あると便利な持ち物
アウトドアチェア
公式戦の場合は次の試合まで時間が空くことが多いです。
待ち時間が長いときにあると便利なのが、アウトドアチェアです。
アウトドアチェアがあればお尻も痛くならないですし、雨の日などで腰を下ろせない場合などにも重宝します。
アウトドアチェアは荷物の多さや練習・試合の時間などを加味して必要なものを用意するのが良いです。


アウトドアクッション
アウトドアチェアより、よりコンパクトに持ち運べるアウトドアクッションもあります。
ただ、雨が降った後などは使いにくいので、アウトドアチェアのほうが便利かなと感じます。
クーラーボックス
チームで用意している所も多いですが、持って行ったほうが無難です。
選手も使うので汚れた手で扱うことも多いですし、飲み物の取り間違いがあった場合かなり気まずいです。。
疲れた時などに座れるようにクーラーバッグではなく、出来ればクーラーボックスがおすすめです。
子供がサッカーを始める際に必要なサッカーグッズなどは以下にもまとめています。
良かったら参考してください。


これだけは守りたい最低限の観戦マナー


ここからは、はじめて子供のサッカー観戦に向かう際に、押さえておきたい最低限のマナーについてご紹介したいと思います。
我が子のサッカーを応援していると、ついつい熱くなってしまうのは誰でもそうです。
しかし、行き過ぎる痛い親って必ず居るんです。。
周りも距離を取り出し、居場所が無くなり、最終的にチームを去っていく親子が多いです。
不自然な時期にチームに移籍してくるご家庭はこのパターンが多いです。
正直、子供がかわいそうですね。親が原因でサッカーを辞めてしまう可能性もあると思います。
子供が伸び伸びサッカーを楽しめるように、これからご紹介する観戦マナーも少しで良いので意識して頂ければと思います。
監督、コーチ、審判をリスペクトしよう
サッカー少年団の場合は、お父さんコーチが毎週練習を取りまとめ、チーム日程を管理して、練習試合などの審判を担当します。
雨の日も、炎天下の日も、真冬の凍える日もボランティアです。
さらに、公式戦でも別チーム同士の試合の審判として駆り出されます。
公式戦での審判を担当するためには講習会にも参加する必要があります。
そして、公式戦では責められることは有っても、褒められることは決してありません。。
子供は親の姿勢を見て学びます。
少年サッカーに携わらる全ての方々を、しっかりリスペクトしましょう。
自分の子供以外の選手も応援しよう
自分の子供しか応援しない親、本当に多いです。
応援しないだけならまだしも、コーチやチームメイトを罵倒する親まで居ますからね。。
サッカーを通して子供に学んで欲しいことはなんですか?
運動神経やボールテクニックだけですか??
サッカーというチームスポーツの意味を、もう一度意識してください。
怒ったり注意しても子供は急にうまくなりません
「前から当たれ!」や「蹴れ!蹴れ!」などの指示のようなコーチングも極力抑えたほうが良いです。
良かれと思ってポジショニングなどをコーチングしたい気持ちもわかりますが、子供が試合中に判断する貴重な機会を奪ってしまいます。
相手チームは敵ではありません。サッカー仲間です
相手チームからガッツリ削られると、確かに声を荒げたくなる気持ちはわかります。
ただ、相手も一生懸命です。そしてただただスキルが低い場合もあります(笑)
どんなに相手が荒くても、まずは最後まで試合を観戦してください。
行動するのはそこからでも遅くないです。
そして、、覚悟を決めたら、まずは自チームのコーチと相談しましょう。
GOサインが出たら、相手チームのコーチ陣に突撃してください(笑)
悪質なチーム(チーム方針)から、子供たちを守るのも大人の役目です。
ただ、悪質なチームの場合でも、相手チームの子供ではなく必ずコーチに異議を唱えましょう。
子供は巻き込まず、あくまで大人同士で穏便に解決するべきです。
知っているとより観戦を楽しめるポイント!


さて、心機一転!
ここからは、知っているとよりサッカー観戦が楽しくなるポイントをあげていきたいと思います!
サッカーの基本的なルールを覚えよう
何はともあれ、まずはサッカーの基本的なルールを覚えておきましょう。
少年サッカーは8人制サッカーが主流
通常のサッカーは11人対11人の11人制サッカーです。
しかし、少年サッカーの主流は8人対8人の8人制サッカーになります。
8人制サッカーは人数が少ないためボールに触れる機会が多いので、選手育成の観点から少年サッカーでは8人制サッカーが普及しています。
8人制サッカーのフォーメーションや重要なポジションなどを以下にまとめていますので、良かったら合わせてご覧ください。


オフサイドを覚えよう!
サッカーのルールの中で、大体皆さん理解出来ていないのがオフサイドだと思います。
むしろ、オフサイドだけ覚えていれば、少年サッカーのルールはすべて理解したようなものです(笑)
オフサイドは攻撃側の反則になります。
以下の条件が揃った場合に攻撃側のオフサイドとなり、守備側のプレースキックからゲームが再開されます。
簡単にまとめると、以下の2つの条件を同時に満たすとオフサイドになります。
- ボールより前にいる味方にボールが渡る
- ボールを受けた味方の前に相手が一人しかいない
①の条件は、パスだけでなくシュートも含まれます。
②の条件の相手とは大体の場合はゴールキーパーが該当します。
そして、見方がボールを受けた時にオフサイドが判断されるのではなく、その前のボールを蹴った瞬間にオフサイドかを判断します。
例えば、以下のような図の場合はオフサイドです。
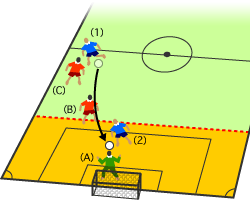
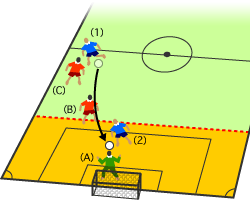
また、味方のシュートのこぼれ球を詰めた場合もオフサイドになる場合があります。
以下のような図の場合もオフサイドです。
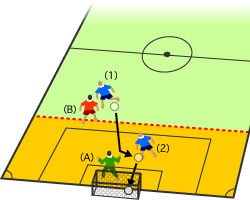
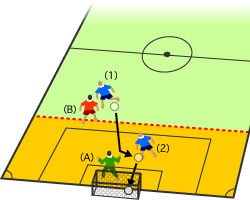
このほかにも、自陣ではオフサイドが取られないなど色々ありますが、まずはこの2パターンだとオフサイドになることを理解しておけば十分です。
オフサイドのルールの詳細については、こちらのサイトでも詳しく解説されています。
http://www.sports-rule.com/soccer/offside/index.html
チームメイトを知ろう
チームに入ったばかりでは、チームメイトについて詳しくないことは当然ですよね。
ただ、普段の練習や試合、そして合宿などを通して、チームメイトのことを良く知っていくと少年サッカーをより楽しめます。
この子はどんな性格でどういった時に力を発揮するのか。
この子はこのプレーをずっと練習してきたから、誰にも負けない。
チームメイトのこれまでの背景を知っていると、公式戦もよりドラマティックに感じてしまいます(笑)
チームメイトをよく知るためにも、出来れば普段の練習やサッカー以外のイベントにも参加できると良いと思います。
子供の良かったプレーを3つ以上覚えておこう
良かったプレーを3つ以上覚えておいて、試合の帰り道などに子供に伝えてあげましょう。
なんだかんだ子供は、親にしっかり見てもらえると喜ぶものです。
また、プレーの結果を褒めるのではなく、そのプレーを選択したことを褒めてあげるとより良いですね。
少し難しくなりますが、なぜそのプレーを選択したのか、他にプレーの選択肢はあったのか、次に似たような機会があったらどうするか、子供と話し合うことはとても有意義です。
まとめ
ここまで長々と書いてしまいましたが、少年サッカーは正直、子供より親のほうが楽しめる部分もあります(笑)
ただし、あくまでも主役は子供であり、親は子供のサポーターという意識を持ち続けて欲しいなと思います。
暑い日も寒い日も、うまくいかない日もあると思います。
それでも、サッカーをやっていて良かったと子供が思ってくれるように、お互い頑張りましょう!




































